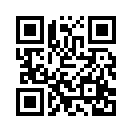2019年09月13日
プチャーチン衣装帰ってきました。
帰ってきました。
港まつりのパレードで活躍しました。ロシアの方からプレゼントされました。当時のプチャーチンのレプリカ衣装、士官、水兵衣装がクリーニングより戻り本日飾りました。
日ロ交流の原点である戸田ならではの展示です❗️☺️


港まつりのパレードで活躍しました。ロシアの方からプレゼントされました。当時のプチャーチンのレプリカ衣装、士官、水兵衣装がクリーニングより戻り本日飾りました。
日ロ交流の原点である戸田ならではの展示です❗️☺️


2019年04月16日
日ロ交流写真展
沼津市戸田のロシアとの交流の歴史に感動した、
ロシアの写真家「アスミルコ ヴラジーミル」氏は、
この文化と向き合う現在の戸田の写真を取り、日ロ交流モスクワ写真展を開催した。
日ロ交流モスクワ写真展のオープニングの様子
http://chanks.i-ra.jp/c99656.html
この写真店は、2018年ロシアにおける日本年の認定行事となり、話題となり盛況のうちに膜を閉じた。
そして、今度は日本で開催する運びとなりました。
その名は
「日ロ交流(凱旋)写真展」
沼津市から開催をスタートします。


催事名:日ロ交流写真展
プラサヴェルデキラメッセエントランスギャラリー
開催日:6月8日~6月20日
道の駅くるら戸田
開催日:7月12日~8月1日
ロシアと戸田との関わりについて
http://chanks.i-ra.jp/e1123345.html
お問合せ:日露交流写真展友好会 0558-88-3212 事務局 石原
続きを読む
ロシアの写真家「アスミルコ ヴラジーミル」氏は、
この文化と向き合う現在の戸田の写真を取り、日ロ交流モスクワ写真展を開催した。
日ロ交流モスクワ写真展のオープニングの様子
http://chanks.i-ra.jp/c99656.html
この写真店は、2018年ロシアにおける日本年の認定行事となり、話題となり盛況のうちに膜を閉じた。
そして、今度は日本で開催する運びとなりました。
その名は
「日ロ交流(凱旋)写真展」
沼津市から開催をスタートします。


催事名:日ロ交流写真展
プラサヴェルデキラメッセエントランスギャラリー
開催日:6月8日~6月20日
道の駅くるら戸田
開催日:7月12日~8月1日
ロシアと戸田との関わりについて
http://chanks.i-ra.jp/e1123345.html
お問合せ:日露交流写真展友好会 0558-88-3212 事務局 石原
続きを読む
2014年10月09日
紀州家から伝わった御船唄
2004年1月1日沼津朝日さんの記事に戸田のご紹介をTOPページにしていただいてます。
「紀州家から伝わった御船唄」
県指定文化財の「戸田の漁師踊り・漁師唄」。漁師唄は、御船唄(せきふね)と祝歌に分けられ、祝歌には江戸末期から行われるようになった大漁を願う漁師踊りがついている。
お船唄は、1629年~43年の寛永年間に紀州の儒学者によって作詞された。「黄帝(皇帝)」「松」「初春」「月見」「酒」「いなり」「さくら」の7曲は紀州家御用船の舟歌として歌われていたもので、1777年(安永6年)、戸田の漁名主・船名主の勝呂家(現在は千本中町で医院を開業)が、紀州家から千石船を拝領した時に伝えられた。
千石船は、井田などで切り出した石を江戸や紀州に運ぶためのもので、江戸城構築などに使われた。
毎年1月2日、勝呂家に漁師が招待され、紀州家から頂いた鯨の肉を肴にして歌い始めるのを慣例とし、明治維新まで続けられたという。現在では、戸田村漁師踊り保存会の人々によって継承されている。
漁師踊りの中には、戸田村で行われていた鯨漁にちなんだ「鯨突き(突き棒)」もある。

なんで一生懸命に漁師踊り保存会の方が継承してるのか、この記事でわかりました石原です。
「紀州家から伝わった御船唄」
県指定文化財の「戸田の漁師踊り・漁師唄」。漁師唄は、御船唄(せきふね)と祝歌に分けられ、祝歌には江戸末期から行われるようになった大漁を願う漁師踊りがついている。
お船唄は、1629年~43年の寛永年間に紀州の儒学者によって作詞された。「黄帝(皇帝)」「松」「初春」「月見」「酒」「いなり」「さくら」の7曲は紀州家御用船の舟歌として歌われていたもので、1777年(安永6年)、戸田の漁名主・船名主の勝呂家(現在は千本中町で医院を開業)が、紀州家から千石船を拝領した時に伝えられた。
千石船は、井田などで切り出した石を江戸や紀州に運ぶためのもので、江戸城構築などに使われた。
毎年1月2日、勝呂家に漁師が招待され、紀州家から頂いた鯨の肉を肴にして歌い始めるのを慣例とし、明治維新まで続けられたという。現在では、戸田村漁師踊り保存会の人々によって継承されている。
漁師踊りの中には、戸田村で行われていた鯨漁にちなんだ「鯨突き(突き棒)」もある。
なんで一生懸命に漁師踊り保存会の方が継承してるのか、この記事でわかりました石原です。
2014年09月26日
「日本で最初に」枕詞付くものが戸田にはいくつもある!
2004年1月1日沼津朝日さんの記事に戸田のご紹介をTOPページにしていただいてます。
「日本で最初に」枕詞付くもの
についての記事です。
西洋帆船建造の他にも、戸田村には「日本で最初に」の枕詞がつくものがいくつかある。
戸田村には、1898年(明治31年)に建てられた東京帝国大学の最も古い寮があった関係で、水泳部が水泳場を開設。水泳場といってもプールではなく、海に折り返し(ターン)施設を設置したもので、1917年(大正6年)、ここに有力選手が集まり、第1回全国競泳大会が盛大に開催されたという。
第4回大会では、旧制茨城中の選手が洋書を基に研究したクロール英法で優勝している。当時の泳法は、片手抜き、小抜きで、クロールは画期的だった。
また、大正時代にモーターボートを所有していた東大は、戸田湾内で当時アンカープレーンと呼ばれた、戸板による水上スキーを楽しんだ。これらのことから、戸田村は日本のウォータースポーツの発祥の地となった。
さらに、1956年(昭和31年)11月「宗谷」で東京港を出航した第1次南極観測隊の西堀榮三郎越冬隊隊長や永田雅美隊員らは戸田村で合宿し、越冬のためのトレーニングを積んだ。当時は2ヶ月に及ぶ航海の末に南極に着いたが、今では飛行機で簡単に行けるようになった。

この記事を見るとマリンスポーツの発祥の地であり、水泳のクロール泳法発祥の地みたいに感じる(⌒▽⌒)
何か知らないことばかりで驚きますが、こんな小さな戸田がすごいところだと改めて思いました。
管理人石原がお届けしました。
「日本で最初に」枕詞付くもの
についての記事です。
西洋帆船建造の他にも、戸田村には「日本で最初に」の枕詞がつくものがいくつかある。
戸田村には、1898年(明治31年)に建てられた東京帝国大学の最も古い寮があった関係で、水泳部が水泳場を開設。水泳場といってもプールではなく、海に折り返し(ターン)施設を設置したもので、1917年(大正6年)、ここに有力選手が集まり、第1回全国競泳大会が盛大に開催されたという。
第4回大会では、旧制茨城中の選手が洋書を基に研究したクロール英法で優勝している。当時の泳法は、片手抜き、小抜きで、クロールは画期的だった。
また、大正時代にモーターボートを所有していた東大は、戸田湾内で当時アンカープレーンと呼ばれた、戸板による水上スキーを楽しんだ。これらのことから、戸田村は日本のウォータースポーツの発祥の地となった。
さらに、1956年(昭和31年)11月「宗谷」で東京港を出航した第1次南極観測隊の西堀榮三郎越冬隊隊長や永田雅美隊員らは戸田村で合宿し、越冬のためのトレーニングを積んだ。当時は2ヶ月に及ぶ航海の末に南極に着いたが、今では飛行機で簡単に行けるようになった。
この記事を見るとマリンスポーツの発祥の地であり、水泳のクロール泳法発祥の地みたいに感じる(⌒▽⌒)
何か知らないことばかりで驚きますが、こんな小さな戸田がすごいところだと改めて思いました。
管理人石原がお届けしました。
2014年09月16日
IHIの基礎から造船日本へ
2004年1月1日沼津朝日さんの記事に戸田のご紹介をTOPページにしていただいてます。
今回は、「IHIの基礎から造船日本へ」についての記事の報告です。

----------------------------------------
IHIの基礎から造船日本へ
不要となったヘダ号はロシアの手で船体と泉質を装飾され、謝意として大砲五十二門を添えて幕府に寄贈された。その後明治15年(1882年)にロシア艦船が戸田港を訪れ、交流が始まった。
また、1887年、プチャーチンの娘のオリガ・プチャーチナは戸田を訪れ、造船ご用係を勤めて提督の世話をした松城家へ宿泊するなどして交流。彼女から贈られた精巧な細工を施したイヤリングは、造船郷土資料博物館に展示されている。
松城家は代々回船業を営み、和風コロニアルノタイルの邸宅には鏝絵の名工・入江長八の作品が多数あり、建築彫刻・絵画においても優れているため、国の有形指定文化財に指定されている。
このヘダ号建造で習得した技術を基に造られた同型船は、君沢軍戸田村の名にちなみ「君沢型ヘダ号」と名付けられ、幕府の軍艦として海の防衛に活躍した。
この時陣頭指揮した戸田村大中島生まれの上田寅吉らが石川島造船所、後の石川播磨重工業(IHI)の礎を築き、「造船日本」へつながった。村内に顕彰碑が立つ。
戸田号の建造時に使われた設計図や道具、ロシア人が持っていた双眼鏡やコンパス、スプーン、フォークなどは、1969年、1969年御浜に建てられた戸田造船郷土博物館に展示されている。
同博物館建設時、当時共産主義国家だったソ連との交流を疑問視する声が県議会にあったという。
----------------------------------------
この新聞記事によると、戸田は日本造船に大きな役割を果たしたと言っているようだ。
今回は、「IHIの基礎から造船日本へ」についての記事の報告です。
----------------------------------------
IHIの基礎から造船日本へ
不要となったヘダ号はロシアの手で船体と泉質を装飾され、謝意として大砲五十二門を添えて幕府に寄贈された。その後明治15年(1882年)にロシア艦船が戸田港を訪れ、交流が始まった。
また、1887年、プチャーチンの娘のオリガ・プチャーチナは戸田を訪れ、造船ご用係を勤めて提督の世話をした松城家へ宿泊するなどして交流。彼女から贈られた精巧な細工を施したイヤリングは、造船郷土資料博物館に展示されている。
松城家は代々回船業を営み、和風コロニアルノタイルの邸宅には鏝絵の名工・入江長八の作品が多数あり、建築彫刻・絵画においても優れているため、国の有形指定文化財に指定されている。
このヘダ号建造で習得した技術を基に造られた同型船は、君沢軍戸田村の名にちなみ「君沢型ヘダ号」と名付けられ、幕府の軍艦として海の防衛に活躍した。
この時陣頭指揮した戸田村大中島生まれの上田寅吉らが石川島造船所、後の石川播磨重工業(IHI)の礎を築き、「造船日本」へつながった。村内に顕彰碑が立つ。
戸田号の建造時に使われた設計図や道具、ロシア人が持っていた双眼鏡やコンパス、スプーン、フォークなどは、1969年、1969年御浜に建てられた戸田造船郷土博物館に展示されている。
同博物館建設時、当時共産主義国家だったソ連との交流を疑問視する声が県議会にあったという。
----------------------------------------
この新聞記事によると、戸田は日本造船に大きな役割を果たしたと言っているようだ。
2014年09月04日
戸田を紹介シリーズby2004年1月1日沼津朝日記事より
2004年1月1日沼津朝日さんの記事に戸田のご紹介をTOPページにしていただいてます。
今回は。戸田の人が芝居好きだという内容の記事の報告です。

江川担庵も認めた芝居好き
村内には代表的な神社が二つあり、橘姫命(たちばなひめのみこと)を祭る御浜埼先端に鎮座する諸口(もろくち)神社、もう一つは大國主命(おおくにぬしのみこと)祭神とする部田(部田)神社。
御浜神社とも呼ばれる諸口神社は漁業の神で、大瀬神社と同じ4月3日、4月4日祭りが行われ、戸田の地名一説にもなってる部田神社は農業の神で例祭日は10月9日。
祭り当日、どちらの神社には回り舞台が設けられ、芝居好きの村民は江戸から役者を呼んで興行を打っていたというが、現在でも歌手を呼び歌謡ショーなどが行われている。
諸口神社の位置
部田神社の位置
戸田村を領内に持つ韮山代官の江川太郎左衛門に「戸田村民は芝居好きだから、収める年貢が少ない」と言われた、との話も伝わるほどの芝居好きだったという。
海と山の幸に恵まれた戸田村は経済的に豊かだった。旦那衆は旅芸人を家に泊め、浄瑠璃や義太夫などの語りを習ったと言うし、弘法さん(弘法大師)や清正さん(加藤清正)などの季節ごとの行事も多かった。
また、清水次郎長一家がいさば(八丁櫓の和船)で戸田をおとづれ、賭場を開帳したという。
今回は。戸田の人が芝居好きだという内容の記事の報告です。
江川担庵も認めた芝居好き
村内には代表的な神社が二つあり、橘姫命(たちばなひめのみこと)を祭る御浜埼先端に鎮座する諸口(もろくち)神社、もう一つは大國主命(おおくにぬしのみこと)祭神とする部田(部田)神社。
御浜神社とも呼ばれる諸口神社は漁業の神で、大瀬神社と同じ4月3日、4月4日祭りが行われ、戸田の地名一説にもなってる部田神社は農業の神で例祭日は10月9日。
祭り当日、どちらの神社には回り舞台が設けられ、芝居好きの村民は江戸から役者を呼んで興行を打っていたというが、現在でも歌手を呼び歌謡ショーなどが行われている。
諸口神社の位置
部田神社の位置
戸田村を領内に持つ韮山代官の江川太郎左衛門に「戸田村民は芝居好きだから、収める年貢が少ない」と言われた、との話も伝わるほどの芝居好きだったという。
海と山の幸に恵まれた戸田村は経済的に豊かだった。旦那衆は旅芸人を家に泊め、浄瑠璃や義太夫などの語りを習ったと言うし、弘法さん(弘法大師)や清正さん(加藤清正)などの季節ごとの行事も多かった。
また、清水次郎長一家がいさば(八丁櫓の和船)で戸田をおとづれ、賭場を開帳したという。