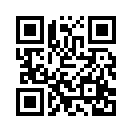2014年10月24日
井田からの富士山が日本一に
2004年1月1日沼津朝日さんの記事に戸田のご紹介をTOPページにしていただいてます。
今回は、戸田の見所の記事第1弾です。
「井田からの富士山が日本一に」
一昨年、週刊誌「日本遺産」の富士山特集の中で、富士山の名称とされる井田からの風景が最高賞を得ている。
「御浜岬公園」
湾内に750メートル突き出た岬の中央部と外海側を通る遊歩道の基点。その昔、魚群を見張ったと言われる「魚見の松」など見事なクロマツが点在する。絶好の富士山眺望地点。
「出逢い岬」
湾口を挟んだ御浜岬北側の外沢海の高台、県道沼津土肥線沿いにある戸田湾と駿河湾を見下ろし、富士山を仰ぐ展望地。
「瞽女(ごぜ)展望地」
戸田村を一望できる県道修善寺の戸田峠にある展望地。三味線を弾きながら歌い踊る盲目の女旅芸人「瞽女」が、大雪の中で亡くなった。この瞽女の霊を慰める観音像が建つ。駿河湾越しに遥か牧之原台地が望める。
「明神池」
海の間近にありながら淡水が沸く周囲7百メートルの池で、ヤチボウズが自生する南限の地と言われてるが、定かではない。
戸田の見所の記事第2弾に続きます。 続きを読む
今回は、戸田の見所の記事第1弾です。
「井田からの富士山が日本一に」
一昨年、週刊誌「日本遺産」の富士山特集の中で、富士山の名称とされる井田からの風景が最高賞を得ている。
「御浜岬公園」
湾内に750メートル突き出た岬の中央部と外海側を通る遊歩道の基点。その昔、魚群を見張ったと言われる「魚見の松」など見事なクロマツが点在する。絶好の富士山眺望地点。
「出逢い岬」
湾口を挟んだ御浜岬北側の外沢海の高台、県道沼津土肥線沿いにある戸田湾と駿河湾を見下ろし、富士山を仰ぐ展望地。
「瞽女(ごぜ)展望地」
戸田村を一望できる県道修善寺の戸田峠にある展望地。三味線を弾きながら歌い踊る盲目の女旅芸人「瞽女」が、大雪の中で亡くなった。この瞽女の霊を慰める観音像が建つ。駿河湾越しに遥か牧之原台地が望める。
「明神池」
海の間近にありながら淡水が沸く周囲7百メートルの池で、ヤチボウズが自生する南限の地と言われてるが、定かではない。
戸田の見所の記事第2弾に続きます。 続きを読む
2014年09月16日
IHIの基礎から造船日本へ
2004年1月1日沼津朝日さんの記事に戸田のご紹介をTOPページにしていただいてます。
今回は、「IHIの基礎から造船日本へ」についての記事の報告です。

----------------------------------------
IHIの基礎から造船日本へ
不要となったヘダ号はロシアの手で船体と泉質を装飾され、謝意として大砲五十二門を添えて幕府に寄贈された。その後明治15年(1882年)にロシア艦船が戸田港を訪れ、交流が始まった。
また、1887年、プチャーチンの娘のオリガ・プチャーチナは戸田を訪れ、造船ご用係を勤めて提督の世話をした松城家へ宿泊するなどして交流。彼女から贈られた精巧な細工を施したイヤリングは、造船郷土資料博物館に展示されている。
松城家は代々回船業を営み、和風コロニアルノタイルの邸宅には鏝絵の名工・入江長八の作品が多数あり、建築彫刻・絵画においても優れているため、国の有形指定文化財に指定されている。
このヘダ号建造で習得した技術を基に造られた同型船は、君沢軍戸田村の名にちなみ「君沢型ヘダ号」と名付けられ、幕府の軍艦として海の防衛に活躍した。
この時陣頭指揮した戸田村大中島生まれの上田寅吉らが石川島造船所、後の石川播磨重工業(IHI)の礎を築き、「造船日本」へつながった。村内に顕彰碑が立つ。
戸田号の建造時に使われた設計図や道具、ロシア人が持っていた双眼鏡やコンパス、スプーン、フォークなどは、1969年、1969年御浜に建てられた戸田造船郷土博物館に展示されている。
同博物館建設時、当時共産主義国家だったソ連との交流を疑問視する声が県議会にあったという。
----------------------------------------
この新聞記事によると、戸田は日本造船に大きな役割を果たしたと言っているようだ。
今回は、「IHIの基礎から造船日本へ」についての記事の報告です。
----------------------------------------
IHIの基礎から造船日本へ
不要となったヘダ号はロシアの手で船体と泉質を装飾され、謝意として大砲五十二門を添えて幕府に寄贈された。その後明治15年(1882年)にロシア艦船が戸田港を訪れ、交流が始まった。
また、1887年、プチャーチンの娘のオリガ・プチャーチナは戸田を訪れ、造船ご用係を勤めて提督の世話をした松城家へ宿泊するなどして交流。彼女から贈られた精巧な細工を施したイヤリングは、造船郷土資料博物館に展示されている。
松城家は代々回船業を営み、和風コロニアルノタイルの邸宅には鏝絵の名工・入江長八の作品が多数あり、建築彫刻・絵画においても優れているため、国の有形指定文化財に指定されている。
このヘダ号建造で習得した技術を基に造られた同型船は、君沢軍戸田村の名にちなみ「君沢型ヘダ号」と名付けられ、幕府の軍艦として海の防衛に活躍した。
この時陣頭指揮した戸田村大中島生まれの上田寅吉らが石川島造船所、後の石川播磨重工業(IHI)の礎を築き、「造船日本」へつながった。村内に顕彰碑が立つ。
戸田号の建造時に使われた設計図や道具、ロシア人が持っていた双眼鏡やコンパス、スプーン、フォークなどは、1969年、1969年御浜に建てられた戸田造船郷土博物館に展示されている。
同博物館建設時、当時共産主義国家だったソ連との交流を疑問視する声が県議会にあったという。
----------------------------------------
この新聞記事によると、戸田は日本造船に大きな役割を果たしたと言っているようだ。
2014年08月29日
戸田を紹介シリーズby2004年1月1日沼津朝日記事より
2004年1月1日沼津朝日さんの記事に戸田のご紹介をTOPページにしていただいてます。
私石原自身も知らないことが書かれていて驚きました。
その記事の内容を何回かに分けてご紹介をさせていただきます。
沼津市と合併する前の新聞記事ですが、最近手に入りましたのでご紹介をしていきます。

---------------------------------------
題「歴史と自然 海、山の幸豊な戸田村を訪ねて」
天然の良港、のどかな地
話題の戸田はどんな所・・・身近にある良さ、改めて探る
1939年に開催されたニューヨーク国際博覧会の日本館に展示された日本紹介のパノラマ写真が、達磨山から内浦湾越しに富士山を望んだものだったことを知る沼津市民は少ないが、人は得てして、身近にある「良さ」に気づかないもの。沼津市南部と接する「戸田村」の良さを探ってみた。
丸塚古墳・松江古墳について冒頭に書いてあります。
村の成り立ちから見ると、古墳時代(弥生時代に次いで、ほぼ三世紀末から七世紀に至る)後期の6世紀前半、小山田、上野、熊野、沢海(たくみ)井田の地に小規模な集落が誕生。
6世紀末後半、井田地区には新羅(しらぎ=古代朝鮮の国名、356年~935年)系の有力な支配者が渡来し、駿河湾の交通を掌握する伊豆半島でも一級の部族として勢力を伸ばした。彼らは、井田の海に開かれた港を生活の糧として、伊豆半島西海岸の田子あたりまで支配していたという。
この支配者と家族の墓が井田の丸塚と松江(すんごう)、戸田の沢海と根岸に造営され、古墳群となっている。松江古墳群が初めて書物に現れるのは寛政12年(1800年)に書かれた「豆州志稿」。
これらの古墳は駿河湾を取り巻く古墳時代後期の特徴を持った遺跡で1984年9月戸田村指定の遺跡となった。
遺跡からは縄文期のあしあとを残す黒曜石の矢尻や土器、土器片など出土し、紀元前3000年から2000年ほど前からこの地に人が住んでいたことが推測される。
---------------------------------------
富士山の見える高台に松江(すんごう)古墳はあります。
煌きの丘と隣接する場所です。そちらに行けば、この見晴らしの良いところに墓を作っている先祖の凄さをわかるのかもしれません。
煌きの丘紹介ページへリンク ←ぽちっ 続きを読む
私石原自身も知らないことが書かれていて驚きました。
その記事の内容を何回かに分けてご紹介をさせていただきます。
沼津市と合併する前の新聞記事ですが、最近手に入りましたのでご紹介をしていきます。
---------------------------------------
題「歴史と自然 海、山の幸豊な戸田村を訪ねて」
天然の良港、のどかな地
話題の戸田はどんな所・・・身近にある良さ、改めて探る
1939年に開催されたニューヨーク国際博覧会の日本館に展示された日本紹介のパノラマ写真が、達磨山から内浦湾越しに富士山を望んだものだったことを知る沼津市民は少ないが、人は得てして、身近にある「良さ」に気づかないもの。沼津市南部と接する「戸田村」の良さを探ってみた。
丸塚古墳・松江古墳について冒頭に書いてあります。
村の成り立ちから見ると、古墳時代(弥生時代に次いで、ほぼ三世紀末から七世紀に至る)後期の6世紀前半、小山田、上野、熊野、沢海(たくみ)井田の地に小規模な集落が誕生。
6世紀末後半、井田地区には新羅(しらぎ=古代朝鮮の国名、356年~935年)系の有力な支配者が渡来し、駿河湾の交通を掌握する伊豆半島でも一級の部族として勢力を伸ばした。彼らは、井田の海に開かれた港を生活の糧として、伊豆半島西海岸の田子あたりまで支配していたという。
この支配者と家族の墓が井田の丸塚と松江(すんごう)、戸田の沢海と根岸に造営され、古墳群となっている。松江古墳群が初めて書物に現れるのは寛政12年(1800年)に書かれた「豆州志稿」。
これらの古墳は駿河湾を取り巻く古墳時代後期の特徴を持った遺跡で1984年9月戸田村指定の遺跡となった。
遺跡からは縄文期のあしあとを残す黒曜石の矢尻や土器、土器片など出土し、紀元前3000年から2000年ほど前からこの地に人が住んでいたことが推測される。
---------------------------------------
富士山の見える高台に松江(すんごう)古墳はあります。
煌きの丘と隣接する場所です。そちらに行けば、この見晴らしの良いところに墓を作っている先祖の凄さをわかるのかもしれません。
煌きの丘紹介ページへリンク ←ぽちっ 続きを読む